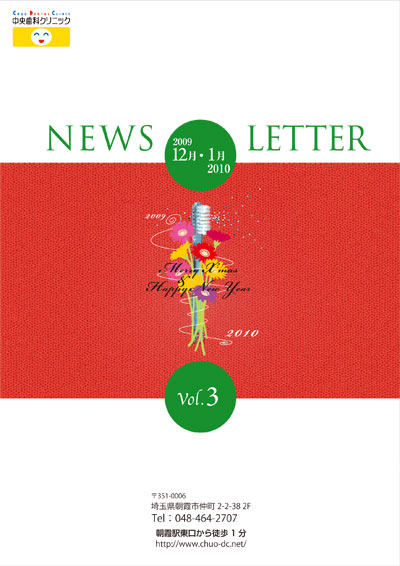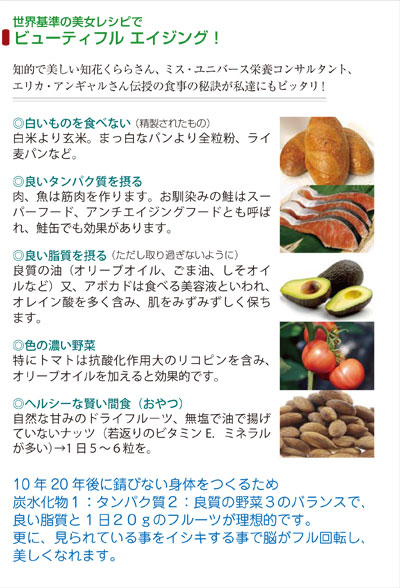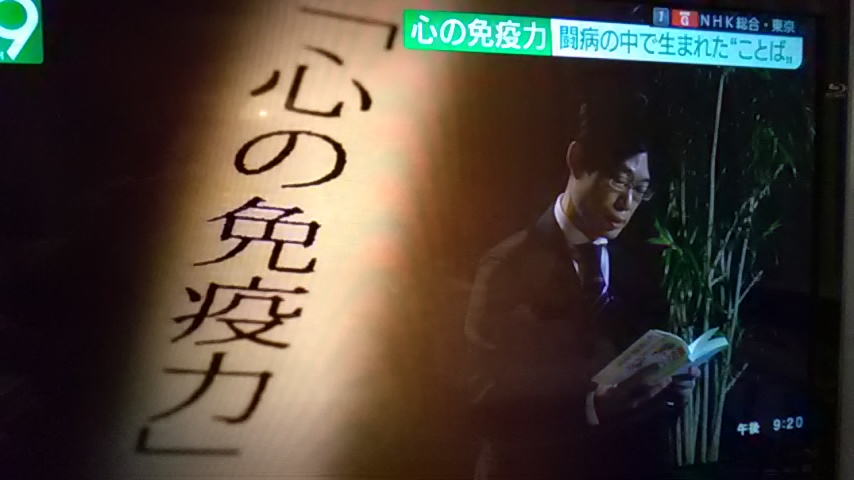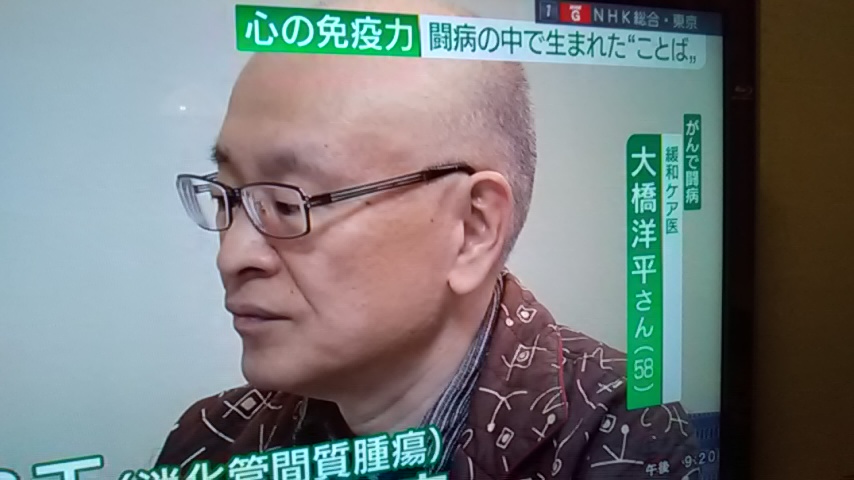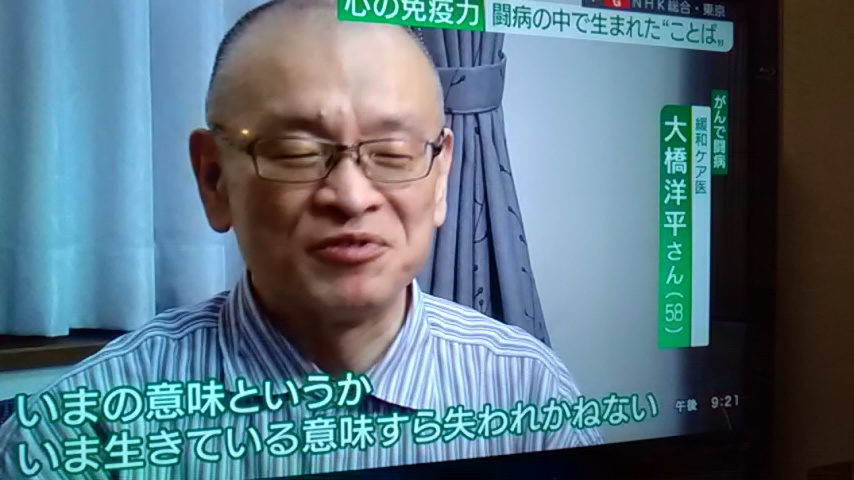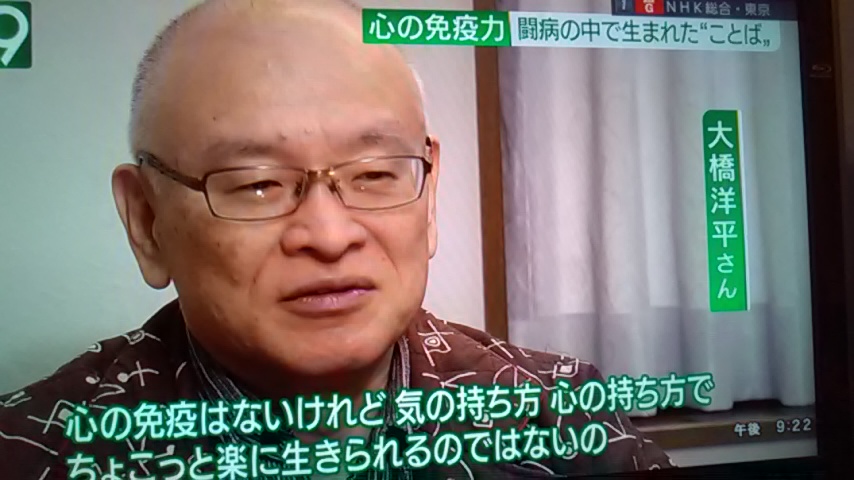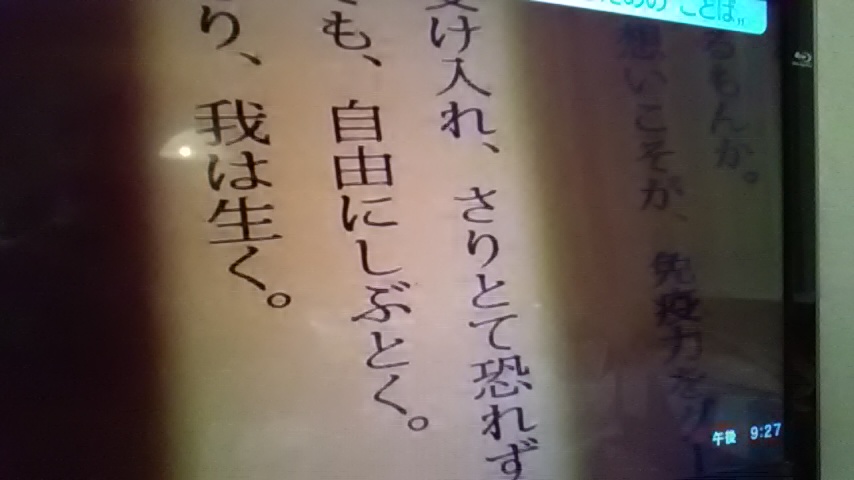もう随分前、この著者・中村桂子さん(東大大学院ご卒業後、三菱化成生命科学研究所人間・自然研究部長)を何かのTVで拝見し、その静かな雰囲気、豊かな言葉で話される内容に感銘受けました。
その後折に触れTVで拝見した時、研究者でありながら主婦でもあり、お庭の手入れもなさりながらで身近に感じられ、なお一層ご発言が気になる方となりました。
堅実でステキな方だなぁと。
立ち読みしてこの本に出会えたのも幸運でした。
「人間はいきものであり、自然の中にある」このあたりまえの原点。
日常感覚と思想を持った科学者が育つ社会づくりへ、と本の帯にはあります。
問題は人間だと。
命を持つ生きものの一つであり、自然の一部である人間。
それから重ね描きのできる人間。
これあっての科学、そして科学技術であり、社会であるわけだと。
今は「経済成長が重要でありそれを支える科学技術を振興する」と言う亡霊のような言葉が飛び交っている。ここには人間はいません。経済成長とは具体的にどのようなことで、誰の暮らしがどのように豊かになるのか、幸せになるのかという問いも答えもありませんと。
したがって科学技術についても、イノベーションという言葉だけしかないところに大きな予算をつけることが「振興」とされ、その研究や技術開発によって人々の日常がどのようななるかということは考えられていません。
私たちって人間なんですというあたりまえのことに眼を向けない専門家によって動かされていく社会がまた始まってるとしたら、やはり「科学者が人間であること」という、あたりまえすぎることを言わなければならないと思うのです・・と。
さらに「生きていること」に向き合って「どう生きるか」を考えるというテーマに終わりはありません、と。
「社会の役に立つ」という言葉が、現代科学のあり様を考える上で、重要なキーワードになってるが、視点を「社会」の側に移し、それが科学や科学技術をどう扱ってきたかを考えて見ると・・。過去にスリーマイル島やチエルノブイリで事故は起き、思いがけない自然の力で、思いもよらず深刻な事故が日本で起きました。自然に対して想定はありませんから、事故はいつでも想定外で起きるものだと言えると。
興味深い例としてイギリスで人気の「きかんしゃトーマス」と日本で愛されている手塚治虫の「鉄腕アトム」の主題歌をあげています。
空を超えて ラララ 星の彼方
ゆくぞ アトム ジェットの限り
心やさしい ラララ 科学の子
十万馬力だ 鉄腕アトム
耳をすませ ラララ 目をみはれ
そうだ アトム 油断をするな
心正しい ラララ 科学の子
七つの威力さ 鉄腕アトム
町角に ラララ 海のそこに
きょうも アトム 人間まもって
心はずむ ラララ 科学の子
みんなの友だち 鉄腕アトム (谷川俊太郎 作詞)
手塚さんも谷川さんも思慮深い方であり、単なる科学礼賛者ではない。手塚漫画には、生命の視点から科学技術を考えるという課題がその底に流れていると。しかしアトムは子供たちに夢を与えるものであることが求められているので、どうしても「ラララ 科学の子」になるのです・・と。
一方、イギリスで子供に人気のテレビ番組「きかんしゃトーマス」のテーマソングの一つに「事故が起きるよ」という一節があるのだそうです。
「じこはおこるさ」
・・・・じこがほら おきるよ いきなりくる
ちょうしにのって やってると
バチがあたる
じこがほら おきるよ
いいきになってると
そうさ よそみしてるそのときに
じこは おきるものさ
おもいつきでやると
きっと しっぱいするよ
こううんのめがみは きまぐれだから
ウキウキしてると まっさかさま
わすれないで きをつけてね いつだって
・・・・・”ひょうしきはいくつもあるのにさ、
だいじなものばかりみおとすね”
そんなとき かならずやってくる
にどとやらなければ いいけど・・・・
(マイク・オドネル、ジュニア・キャンベル
訳・山田ひろし)
この歌は、技術、特に等身大を超えてどんどん大きくなっていく技術には制御の難しさがあることを心にとめておかなければならないという基本を示しています。特にいい気になってると事故になるものだよ、だから気を引き締めなければならないよとストレートに子供たちに伝えています。
ここで言ってるのは人間の問題です。
このように、中村さんは本の中で、科学者だけでなく、現代社会に生きる人皆が、それぞれの立場で、日常感覚と思想性に基づくバランス感覚を発揮してこそ、新しい文明、新しい科学への道が開けてくるのだと思うと述べておられます。
日本人の自然核を大事にしながら「重ね描き」の科学を実践していくために子供の教育にも触れ、吉本隆明の自然観にも触れ、吉本が好きな宮沢賢治の考察を実に魅力的と述べています。
賢治のテーマは常に「本当の賢さ」と「本当の幸せ」です。それは生命誌のテーマでもあると。人間は生き物であるという事を基本に置き、そこから人間らしく生きる道を探すとしたら「本当の賢さ」と「本当の幸せ」以外にはないと。
中村さんのこの本は、深く静かに「私たちって人間なんです」という当たり前のことに眼を向けて、又この当たり前のことに眼を向けない専門家によって動かされていく社会がまた始まっているように思えると危惧をし、やはり「科学者が人間であること」という、当たりまえ過ぎることを言わなければならないと思うと繰り返し述べておられます。
小さな新書ですが、中身は重く尚且つ軽やかに、訴えるものが強く心を打ち
手放せない一冊が増えました。